史上最高の猛暑だった2025年の夏! それでも昭和オヤジが心配する「オーバーヒート」に陥るクルマを見かけないワケ
口コミを書く
口コミを見る
WEB CARTOP より

いつの間にか聞かなくなった「オーバーヒート」
10月になって、ようやく秋めいてきました。それにしても、2025年の夏は史上最高に暑い夏でした。気象庁の発表している観測史上最高気温の上位5地点はすべて2025年に記録されていると聞けば、史上最高に暑い夏というフレーズが大げさでないことも理解できるでしょう。
しかしながら、これだけ気温が上がったのに、最近のクルマはほとんどオーバーヒートをしなくなりました。昭和の時代は、ちょっと暑くなるとオーバーヒートにより「エンコ(エンジン故障)」してしまうことが多かったことを考えると、まさに隔世の感ありです。
なぜ、これほど暑さに強くなったのでしょう。
水冷エンジンの冷却液として使われるLLC(ロングライフクーラント)の沸点(許容温度)は、昭和のころから大きく変わったとはいえません。ラジエターほか水冷にかかわる部品の性能や制御が進化していることが、暑さに強いクルマを生んでいるのです。

わかりやすいところでいえば、クーリングファンがあげられます。もともとは走行風によってLLCを冷却するのがラジエターですが、そのアシストをするのがクーリングファンの役割です。
かつて、エンジン縦置きのリヤ駆動(FRレイアウト)が主流だった時代には、クーリングファンはエンジンのクランクシャフトによって直接回す仕組みがスタンダードでした。このシステムの欠点は、エンジン回転数が低いときにはファンの回転も少なくなり、冷却性能が落ちること。渋滞をアイドリングくらいのエンジン回転数で走行しているとファンによる冷却効果が小さくなってしまい、オーバーヒートにつながることが多かったのです。
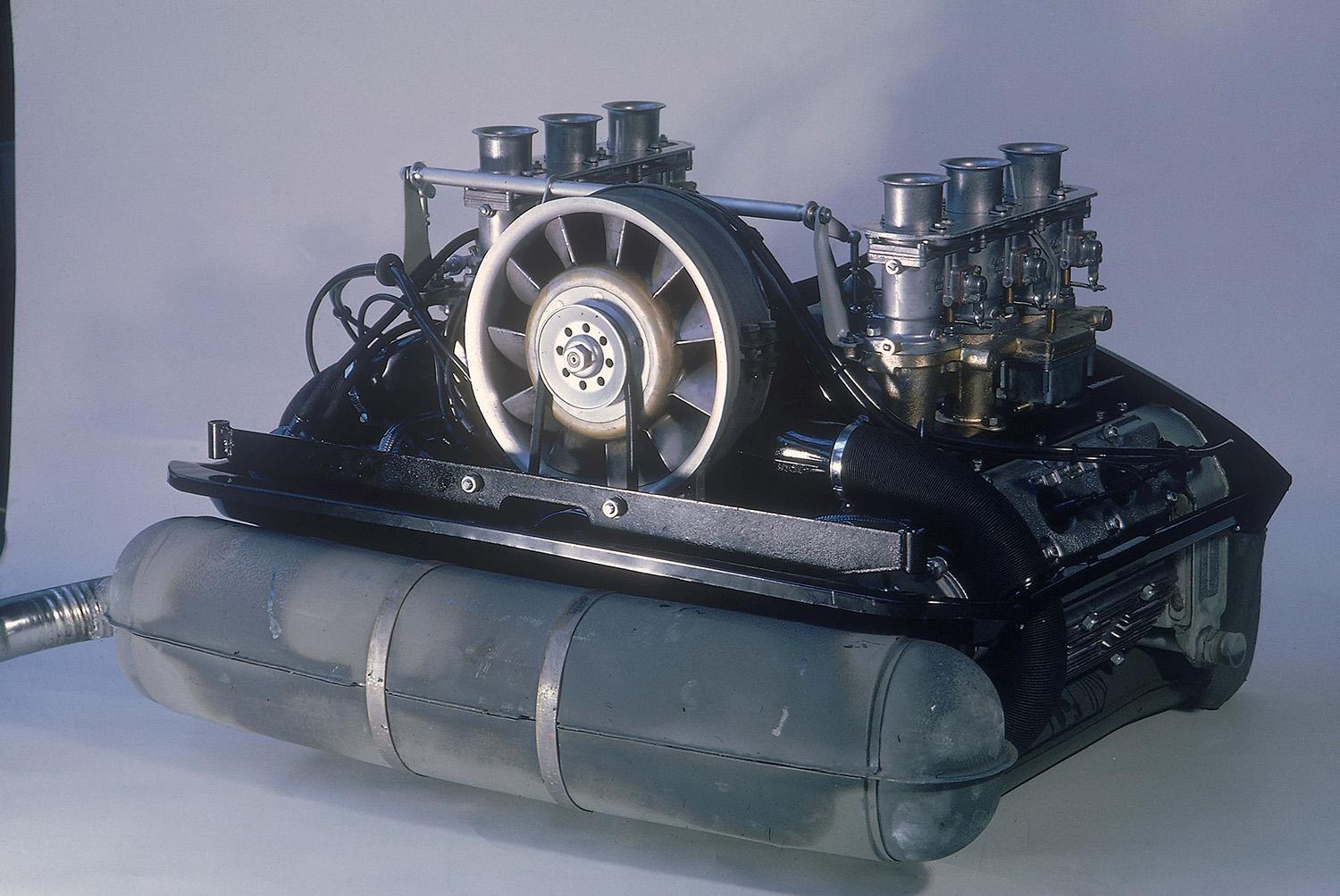
しかし、エンジン横置きのFF車が主流となっていったころから、ラジエターを冷やすクーリングファンの電動化が進みました。エンジンがアイドリングであっても、しっかりファンを回すことができるので、十分に冷却水を冷やすことができるようになったのです。
補器類やエンジン本体の進化も大きい
ハイブリッドカーが増えてきたころから、LLCを循環させるウォーターポンプの電動化も進んでいます。ご存じのように、かつてはウォーターポンプもクランクシャフトによって動かしていました。つまり、エンジン回転数が低いときにはLLCの循環も遅くなっていたのです。
頻繁にエンジンが停止するハイブリッドでは、クランクシャフトによってウォーターポンプを動かしていては十分な冷却性能を発揮できません。その対策として電動ウォーターポンプの採用が増えていったのです。クーリングファン同様、電動化することでウォーターポンプもエンジン回転数と無関係に、水温を維持するための理想的な流量を実現することができます。これも冷却系の性能アップにつながっています。

燃費を重視したエンジン自体の進化も見逃せません。燃料消費を減らすためにエンジンの熱効率を上げることは、排熱が少なくなることにもつながります。エコカーは冷やすべき熱量が減っていると捉えれば、最近のクルマがオーバーヒートしなくなっているのは自然なことなのです。
このように、無駄な発熱を減らし、適切に冷やすメカニズムが進化したことでオーバーヒートを見かけることが少なくなったといえます。
実際、かつての乗用車はどんなに安価なモデルでも水温計を装備していました。その針の様子を見て、オーバーヒートの兆候を感じることは、ドライバーに求められるスキルのひとつだったのです。

しかしいつのころからか、水温計はマストではなくなり、いまや水温が冷えている状態を示す青いランプと、オーバーヒートを示す赤いランプが備わるだけになっています。
機械の破損やメンテナンス不足によるトラブルがなければ、ほぼオーバーヒートとは無縁になったという自動車メーカーの自信が、水温計を省略することにつながったのでしょう。
逆にいうと、水温計を備えているような旧車・ヒストリックカーにおいては、オーバーヒートを早めに察する能力や、そもそもオーバーヒートさせないような運転スキルが必要ともいえます。
そんなスキルのひとつが、真夏にヒーターをガンガン使うというもの。ヒーターの熱源はラジエターですから、暖房を全開にすることでキャビンに熱を放出、それでエンジンを守るという修行のようなテクニックもありました。

その時代をリアルに知っている者からすると、「オーバーヒート」が死語のようになっているほど技術進化を遂げた昨今は、本当に素晴らしい時代になったと感じます。
あなたは、猛暑だった2025年の夏に、オーバーヒートを経験しましたか?




































